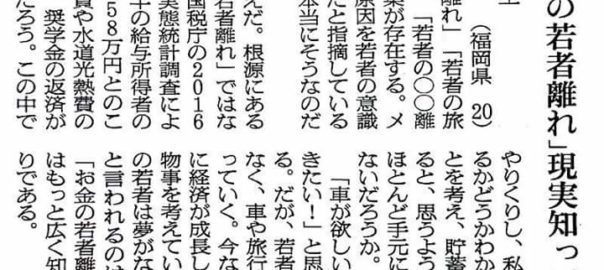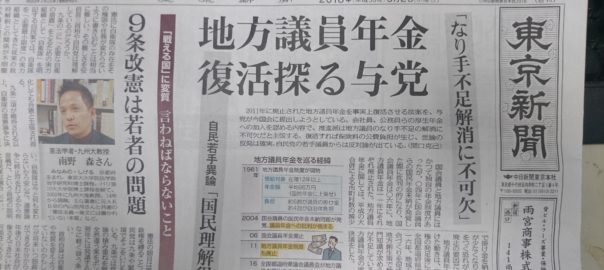「政治家育てる当事者意識持とう」・・有権者の投書から

【有権者が政党、政治家を育てる気概もとう・・朝日新聞の投書から】
昨日(6日)の朝日新聞で、政治家と市民との関係について問う投書が掲載されています。この方の投書では、憲政の父、尾崎行雄の言葉を引き合いにだし、「約70年前、尾崎は明治憲法下で真の政党政治が実現しなかった理由について、『利害や感情によって結ばれる親分子分の関係と同型の私党はできても、主義・政策によって結ばれ、国家本位に行動する公党の精神はどうしても理解できない』と喝破した」「同時に尾崎は『頼まれたから、金をくれたから、義理があるから』一票を入れるという有権者の姿勢も厳しく批判した。『川上の選挙が濁れば、川下も濁る』」「政党や政治家に対する批判が、そのまま我々有権者に跳ね返る。政治を傍観し嘆くだけでは何も変わらない」「政党も政治家も我々の手で育てあげるというくらいの当事者意識が求められている」と結んでいます。
【結城りょうの視点・・政治家も有権者も自立する気概を】
この方の投書を読んで、私も同じ問題意識をもちます。今の安倍総理をめぐる森友、加計疑惑に象徴されているように、政治家の役割とは、税金や国民の財産を、自分を支持する有権者、支援者の利益になるように「引っ張ってくる」ために、官僚、役人をうまく使いこなすことが、実力のある政治家の役割のようになってしまったことが、政治の堕落だを引き起こしていると思います。政治家の周辺には利権をもとめる有権者がむらがり、政治家は自らの選挙地盤、権力基盤を強化するために官僚、役人を使って利権誘導を制度化する。マスコミも権力者の「提灯持ち」をすることで、利益を得る。ここに利権と汚職、権力を私物化する政治家を「良し」とする政治の堕落が起こるのではないでしょうか。今日の日本はその意味でも、国家戦略などなくなり、「その日暮らし」の政治が横行してしまったことが、今日の日本の姿ではないでしょうか。
政治とは本来、国民生活の安寧、国家の平和と安定を実現するためのものであり、国会議員も地方議員も国民、住民の代理人として議会に選出されているわけです。私はそのために何をしなければならないのか、適切な言葉がみつかりませんが、政治家も有権者も自立する社会を政治の責任でつくらなければならないでしょう。尾崎行雄の言葉をかみしめたいと思います。