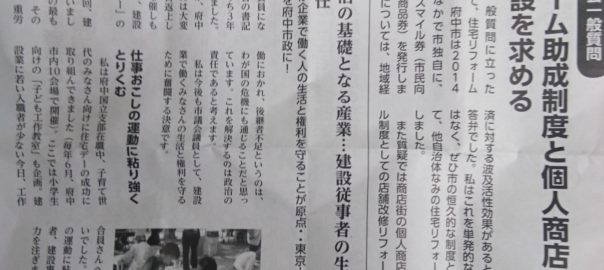府中市議 結城りょうへの応援メッセージ (第二弾)
私、結城りょうへ市民の方から応援メッセージをいただきましたので、再度紹介します。
●市民目線の質問は日ごろの活動から
例年、400名を越える85歳以上の会員を3ヶ月かけて訪問しており、結城さんにも同行してもらっています。独居、孤立高齢、病弱、生活苦など顕著です。市民目線の質問は結城さんのこうした活動に裏付けられたものだと思います。今後も同様に社会的弱者の立場にたった活動を期待しています。(晴見町、健康友の会府中支部 村田公子)
●市議会議員は結城さんの天職!2期目も必ず勝利して!
私が通勤時、結城さんを府中駅北口で始めて、たすきとのぼり旗の街頭宣伝の姿を見かけたのは2015年でした。チラシを受け取り立ち話、日曜版の読者です。東京土建目黒支部の名刺を渡した。彼は「私も府中支部の書記でした」と話され、驚きました。その後も市議になってからも彼は、駅頭と市政、教育問題のブログを発信をして素晴らしい。2期目落としてはならない。毎日更新のブログでは人権問題、原発、格差貧困、外国人労働者、シングルマザー、子ども食堂、何でも深く掘り下げ、わかりやすくときほぐしてくれる。高校生にも読ませたい。今では私も土建府中支部の組合員、もっと顔だしてくださいね。(東京土建府中国立支部組合員、杉本恵二さん)
本当にうれしい応援メッセージです。ますます頑張る決意です。
結城亮(結城りょう)