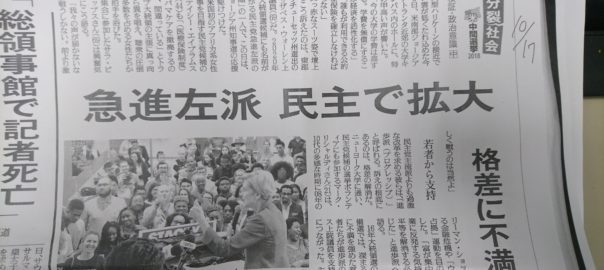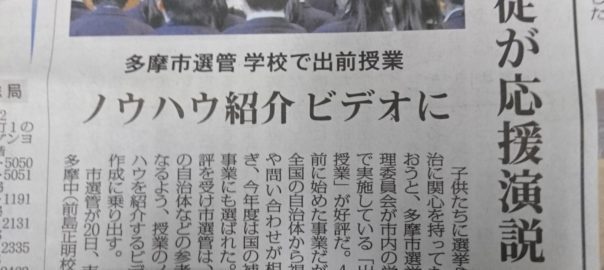年頭に思う 府中で出会ったあのベトナム青年労働者はどこに・・入国管理法改定に思う
【ベトナム青年労働者に対する過酷な労働、人権侵害】
私も府中市の市議会議員になってから多くの生活相談を受けるようになりましたが、印象に残っているのが件あります。それはベトナムの若者でわが国に就労に来ていた青年です。このベトナム青年は母国では貧しい農家の息子さんで、本国に送金もしながら日本の建設会社に従事されていました。しかし、その労働の厳しさと生活環境の苦しさ、また賃金の低いこともあり、「今の環境から逃れたい」と市民の方を通じて私に相談がありました。私は自身が会員でもある、日本ベトナム友好協会の通訳の方にご協力いただき、このベトナム青年と直接話を伺いました。
相談内容は、勤務している建設会社の過酷な労務管理の実態告発、また賃金があまりに安く、母国に送金すると、手元にお金が残らないことでした。このベトナムの青年はその後務めていた建設会社を辞めて、どこかに行ってしまったとのことです。私は昨年の臨時国会で入国管理法改悪の問題が国会で審議されていましたが、外国人技能実習という何の外国人労働者に対する人権侵害の実態が暴露された際、私は真っ先にこの件を思い出しました。
私はベトナムという国に憧れを抱いています。古くは中国、フランスの侵略から撃退し、あのベトナム戦争(抗米救国闘争)では大国アメリカを撃退し、南北ベトナムを統一した、その民族独立の気概に驚嘆し、尊敬の念をもっています。そしてベトナム労働党(共産党)を指導した、ホーチミン主席に心酔しました。2013年の8月にはベトナム戦跡ツアーにも参加して、ベトナムの地を踏みしめたこともあります。私が通訳の方を通じて、「ベトナムの自主独立の歩みと、ホー主席を尊敬しています」とその青年に伝えると、とても嬉しそうな顔をしていたことを今も覚えています。
しかし現在のベトナム青年が我が国で過酷な労働、人権など無視されて働かされている状況を天国のホーチミン主席が見たら、どう思われているでしょうか。
わが国ではリストラによって勤労者も、そして、外国人労働者も使い捨てにされている実態であります。これを正すのが政治の責任であり、共産党の任務であると、私は実感しています。
結城亮(結城りょう)