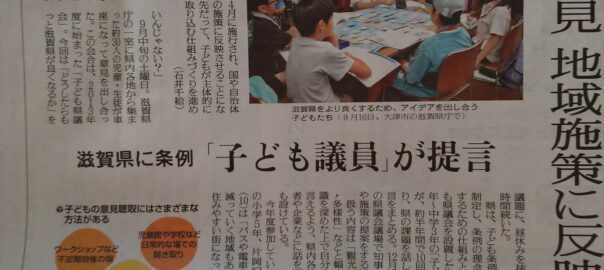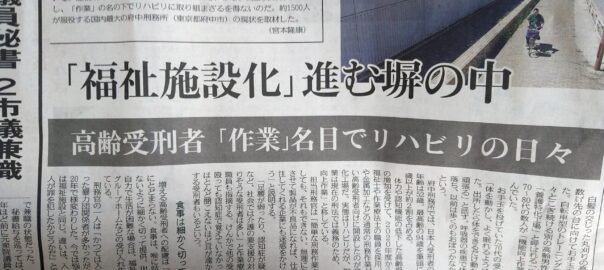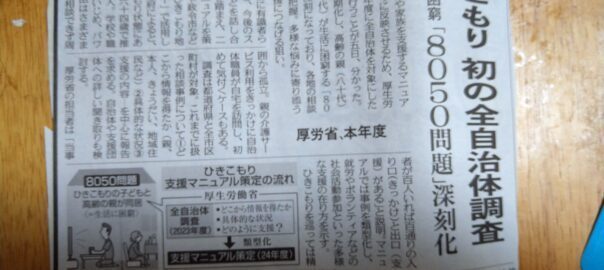(府中市)不登校児童生徒の居場所をどうするべきか・・矢川プラス(国立市)のような、多世代が集える公共施設を設置してほしい(保護者の声)

府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。
不登校児童生徒の居場所の問題で私のブログをご覧になられた保護者の方から、ご意見をいただきましたので、以下紹介させていただきます。
★矢川プラスへ行くことで登校扱いを認めてられるよう検討されている
不登校児のデイルームでの居場所について、気がついたことをお伝えさせていただきたいと思います。国立市にある矢川プラスは、0歳から18歳までの児童が過ごせる児童館が併設されています。幼児ルームと、小学生以上のエリアが完全に分けられています。また、勉強ができるようになっているエリアもあることから、中学生の不登校と思われる学生も独学をしていました。
立川市のフリースクール、「はたけんぼ」の代表が、矢川プラスの運営に携わっていることが原因がわかりませんが、矢川プラスに通えた不登校の児童には、学校の登校扱いにできるようにする話も現在市内で検討されているようです。この登校扱いが立川市で認められるのであれば、府中市でも矢川プラスへ行ったら登校扱いに認められるように検討してほしいと思います。
★矢川プラスは小学生について営業時間の間は、保護者の付き添い無しで、いつ来てもいい
その理由は、家から出れない児童は、起床のリズムや、起立性低血圧、昼夜逆転、引きこもりなどになる可能性もあります。目的を持って午前中から外に出かけることで、整腸作用や運動、良質な睡眠、メリハリのある生活を送ることが出来ます。矢川プラスに遊びに行ってみて、府中市とのあまりの違いに愕然としました。受け付けで登録するときも、小学生は、営業時間の間は、保護者の付き添い無しで、いつ来てもいいと、子供たちに丁寧に説明してくださいました。朝から行っていい居場所に感動しました。府中の「たっち」には、幼児が過ごせるだけで小学生の居場所はありません。新しくできる発達支援センターのデイルームに、保護者付き添いで不登校児の居場所ができることを喜びましたが、よく考えてみれば、「場所の提供のみで、何も環境整備されていない部屋では何も意味がない」と感じました。
★いまの子どもたちは、文化センターにSwitchの電子ゲームを持ってくることができる
不登校児をデイルームでも受け入れをするのでしたら、矢川プラスをお手本にしてほしいです。矢川プラスの児童館では、児童が自ら企画することができるというのも魅力があると感じました。矢川プラスでは、工作に使って良いものが壁一面に置かれていたり、タブレット端末の貸出で絵を書くことができたりします。また、「流行りの」漫画や、本と絵本、たくさんのボードゲーム、勉強できるゾーン、お昼ごはんを食べられる場所を設けてあったので同じようにデイルームにもほしいです。
府中市内の文化センターの遊戯室には、充分な数のボードゲームがありません。オセロ、将棋くらいです。オセロ、将棋があれば充分だと思う方もいるかもしれませんが、時は流れ、いまの子どもたちは、ファミコン世代と違って、文化センターにSwitchの電子ゲームを持ってくることができます。それを目的に集まることもあります。それが悪いとは言いませんが、複数で楽しめるボードゲームをもっとたくさん設置して、画面を見る目を休ませて、児童同士のコミュニケーションを増やしてほしいと思います。
★図書館にも遊戯室にも、デイルームにも、いま流行りの漫画を増やしたり、遊戯室へのボードゲームを充実してほしい
文化センターの図書館には、手塚治虫さんの「火の鳥」「ブラックジャック」の漫画だけです。矢川プラスをお手本にして、図書館にも遊戯室にも、デイルームにも、いま流行りの漫画を増やしたり、遊戯室へのボードゲームを充実することが、文化センターに持ち込んで電子機器のゲームをするよりもずっと健康的だと思います。流行りの漫画を置くことで、不登校児の外出を促すことも可能性があります。卓球台もボードゲームも午前中から利用可能にできたり、せめて午前中も人員を配置するなど検討してほしいです。できなければ、矢川プラスをお手本にした児童館を市内に作ってほしいと思います。
府中市から矢川プラスへ行こうとすると、片道1間かかり、駐車場もないので、不登校や特性のある児童の状態によっては移動が困難です。本来市内にあるべき施設を求めて市外へ利用者が流れていくのはおかしいと思いませんか。不登校児の居場所が府中市にはありません。(保護者の方の声より)
※矢川プラスとは・・まちの「元気」と「未来」をつくる場所(HPより)
矢川プラスは、「ここすきひろば」「児童館」など、子どもや保護者など子育て世代が利用する機能と、「みんなのホール」「みんなのひろば」「多目的ルーム」などの多世代が利用できる機能を同じ建物にまとめた、複合公共施設です。矢川プラスの「プラス」は、フランス語の「place(広場)」と英語の「plus(加える・つながる)」から名付けられました。矢川プラスは、皆さんがつどい、つながり、地域のにぎわいをつくりだし、このまちの元気と未来をみんなでつくってくための拠点です。
※ゆうきりょうのブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情など、また新型コロナ関係でのご要望などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp
★市政の話題など、ブログ毎日更新 検索⇒ゆうきりょう