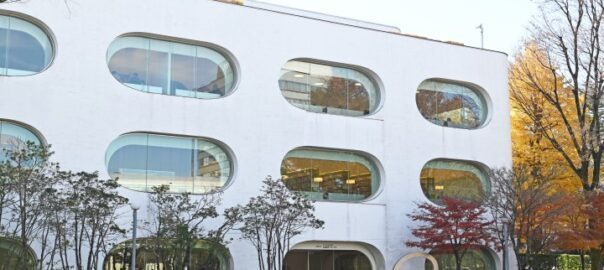府中市 市独自の保健所設置と中核市への移行を求めたい・・「慎重に検討する」府中市令和8年度予算要望書から(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
私が所属する会派「自由クラブ」では、昨年10月、府中市長あてに予算要望書を提出しましたが、そのなかに府中市の中核市への移行と、府中市独自の保健所の設置を求めました。
★府中市の回答⇒「慎重に検討する」
府中市を含む6市を管轄する多摩府中保健所とは、昨年度から本市の保健師が派遣研修するなど、日々密な連携を図り、本市における保健衛生の取組の充実に努めているところです。本市単独での保健所設置に当たっては、圏域内における他自治体との関係性や、現在多摩府中保健所で担っている保健分野以外の業務の所管部署における事情、また、そのコスト面も含めた対応が求められるものと考えております。これらのことも踏まえ、府中市単独での保健所の設置については、中核市への移行とあわせて慎重に検討してまいります。(市の回答より)
★「中核市への移行は財政面でデメリットがあるが、市民へのきめ細やかなサービス提供が可能となる」(市の答弁)
私も24年3月議会の予算委員会(総括質疑)で、府中市が中核市に移行する課題について、質しました。
中核市への移行について、先の市長選挙において高野市長が掲げた政策項目のなかに、掲げられており、私が所属する会派「自由クラブ」も昨年10月に提出した予算要望書のなかで、府中市の中核市への移行を要望していました。今後の府中市の発展を考えた場合、ぜひ実現すべき政策と考えています。
★ゆうきりょうの質問①⇒ 中核市移行について、あらためてその考え、意義について伺います。
★府中市の答弁① ⇒中核市移行については、委譲される各種事務を行うための財源が地方交付税に措置されることから、不交付団体(国からの財源移譲がない)である府中市においては、財政面において大きな負担が生じるなどのデメリットが想定されますが、一方で、保健所の設置など多くの事務が委譲され、より市民に近い、きめ細やかなサービスの提供が可能となることや、これまで以上に自主的なまちづくりが可能となることなど、メリットもあると考えています。
こうしたことから、議会からの意見も踏まえつつ、まずは庁内関係課で中核市移行の検討を進めていますが、中核市移行を検討している候補市として「中核市市長会」に加盟し、先進市から情報収集を行うなど、より幅広い視点で検討を進めていきたいと考えています。
★ゆうきりょうの主張⇒ 中核市への移行については、この間、杉村議員も取り上げ、会派要望もしてきました。この間の市の答弁で一貫しているのは、中核市への移行することで様々な面で、行政サービスが拡充するという前向きな中身なのですが、最後にどうしても「財政面の課題なども考慮しながら長期的な視野で考えていく必要がある」というものです。しかしながら、今回、高野市長が一歩踏み込んで、中核市への移行を視野にいれた政策を公約の1つに加えたことは、将来の府中市を展望する場合、重要な意義をもつものです。
★「(中核市への移行は)財源面も含め、クリアすべき課題があることから慎重に判断すべき」(市の答弁)
★ゆうきりょうの質問②⇒1回目の答弁をうけて、この際、府中市は中核市への移行については、そのタイムスケジュールを立てて、いつまでに中核市に移行するというスケジュールを組み、その計画のなかで財源ねん出も具体的にするべきと考えるが、市の認識を伺います。
★府中市の答弁②⇒現時点においては、あくまで中核市への移行を目指すかどうかを判断するための検討を進めているところであり、具体的いつまでに中核市に移行するというスケジュールについてはもっていません。仮に移行を目指すとしても、先進市の事例を見ますと、機運醸成や市民のみなさんに理解をいただくために、時間をかけて進めているものと認識しています。(以上、市の答弁)
またいずれは中核市への移行を目指すのか、目指さないのか、また目指すとすれば、いつ移行するのかという判断をする時期が来るものと思われますが、中核市への移行については、以前から答弁しているとおり、財源面も含め、クリアすべき課題があることから慎重に判断すべきと考えています。(以上、市の答弁)
★府中市が選ばれる街になるためにも、中核市への移行は重要な課題ではないか
★ゆうきりょうの主張⇒ 行政サイド(事務方)の立場にたつと、中核市への移行という課題は、なかなかハードルが高いものと推察します。これは事務方の立場からすると、それなりの理はあると思います。府中市が中核市へ移行する作業というのは、府中市が今後も存続し、発展するために、府中市が選ばれる街になるために、行政サービスの質的発展、量の拡充をめざす、その礎になる作業ではないだろうかと思うわけです。市職員のみなさん、市の幹部の方々の府中市に対する「志」が試される、重要な任務ではないかと考えるわけです。この課題については、また随時、取り上げていきます。(府中市議 ゆうきりょう)
※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp 電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202
※ 府中市議会議員 ゆうきりょう の朝の駅頭市政報告は、原則、毎朝下記の予定で行っています。駅頭では「市政通信」を配布しています。市政相談、生活相談なども受け付けています。なお雨天時や、自身の都合により中止の場合がありますが、お気軽にお声をおかけください。駅頭には朝8時までいます。
月曜日・・西武線多磨駅東口
火曜日・・京王線多磨霊園駅南口
水曜日・・京王線東府中駅北口
木曜日・・西武線多磨駅西口
金曜日・・京王線多磨霊園駅北口