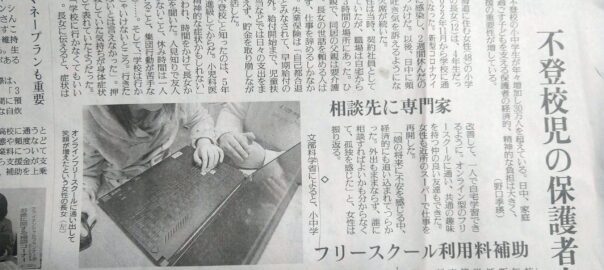府中市 学校いじめ防止・・江戸川区がいじめ「重大事態」を認定、学校側の対応不十分(読売新聞)

府中市議会議員(ブロガー議員、無所属)の ゆうきりょう です。
★江戸川区内の小学校で、年上学年の男子からのいじめを、重大事態に認定
昨日の読売新聞多摩版に江戸川区の小学校に通う児童が、23年1~2月に、「同じ学校の違う学年の児童からいじめをうけて不登校になったとして、区教育委員会がいじめ防止対策推進法に基づく『重大事態』と認定していたことがわかった」と報じています。同記事では「調査報告書によると、被害児童が放課後に自宅外で友達と話していたところ、加害児童が会話に割り込み、『アホ』『バカ』などと発言、手で頭をたたいた。また2月にも加害児童が『死ね』などと発言、被害児童の腹部を手でたたいた」とのことです。
また記事では「報告書では学校側の対応について、被害児童にも非があったかのようにあつかい、謝罪もさせるなど、不十分だったとした」とし、「区教育委員会研究所の所長は『組織的な対応ができていなかった。情報共有のあり方を見直し、早期発見と対応を徹底したい』としている」と話しています。(1月28日付読売新聞多摩版より)
★いじめの「重大事態」も過去最多を記録
以前の朝日新聞に22年度文科省「児童生徒の問題行動・不登校調査」において、いじめの被害者が心身に重大な傷を負う「重大事態」は前年度から3割以上増え、923件で過去最多を記録。そのうち約4割の事案では、「重大な被害を把握する前にいじめと認知していなかった」と報じています。
★いじめと認定せず、いじめが深刻化した事例が増える
同記事によると「『いじめ防止対策推進法』で規定された、①生命、心身、財産に重大な被害が生じた被害がある場合、②被害者が長期欠席を余儀なくされている疑いがある場合に認定さえる」。「①は448件、②は617件」とあります。記事にもありますが、国はいじめの深刻化を防ぐために早期発見、早期対応が重要としえ、教育現場に積極的な認知を呼びかけ「22年度は68万件超」で過去最高となったそうです。
「一方で重大事態も増え、22年度は923件で前年度比30%増」「重大な被害を把握する前にいじめと認知しなかったのは357件、38%を占め、357件のうち151件では、いじめに該当しうるトラブルなどの情報がありながら、いじめと認知していなかった」とあります。
★文科省も事態を鑑み、緊急対策と通達を全国の教育委員会に発出
こうした状況を文科省は「学校としてのいじめの認知や組織的な対応に課題がある」としています。文科省もこうしたいじめの認知件数、重大自害の発生件数が大きく増えたことをうけ、10月に「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」をまとめ、子どものSOSを早くつかむため、心身の異変を察知するアプリや1人1台の端末を使う相談窓口を整備するとしています。また「全国で起きた重大事態報告書を集めて専門家と原因、背景を分析し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの配置も充実させる方針」を掲げています。
また文科省は全国の教育委員会に緊急対策を求める通知を発出し、「いじめの認知と組織的対応を徹底することが、重大事態の発生防止に不可欠」とし、学校現場にいじめの積極的な認知を呼び掛けたとあります。
★府中市においても、いじめ対策防止条例を制定・・いじめの事件で必ず明るみになる、教育委員会による「いじめ隠し」をさせない制度上の担保、早期対応を
いじめの事件が明るみになると、教育委員会によるいじめ隠しということが、必ず問題になります。いじめの真相、真実を明らかにするために、そしていじめ隠しを防ぐためには、教育委員会に制度上の仕組みを担保すること。その意味からも条例の制定、独立した第三者機関の設置によって、透明性、中立性、公平性を確保することが絶対条件であり、府中市教育委員会がこの条件を制度上クリアしたことは、評価できます。いじめ隠しを許さない組織的、制度的担保を明確にし、早期対応で機能していくことを今後も求めていきます。(府中市議 ゆうきりょう)
※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp 電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202