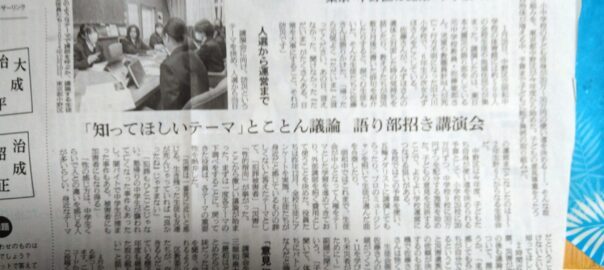府中市 学校現場でのタブレット端末の更新など、ネットワーク再構築に17億円弱予算を投入へ・・府中市令和7年度予算のポイント⑬(府中市議 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
府中市の令和7年度予算のなかに、学校現場でのネットワーク関連の費用が計上されています。
①1人1台のタブレット端末の更新)・・個別最適な学びと協働的な学び実現するため、児童、生徒の1人1台端末の更新を行い、学習指導のさらなる充実を図る。※総額7億4287万円
②現行の教育用ネットワークと校務用ネットワークを統合し、教職員端末の1台化を行うことにより、情報セキュリティ対策の強化、教員の働き方の改善を図る。※総額 9億2317万円
③学校教育ネットワーク再構築事業にともない、教育用と校務用でそれぞれ設けているインターネット回線を、回線速度の改善を図るとともに、1回線に統合する。
④学校教育ネットワーク再構築事業にともない、教員の勤怠管理システムを導入し、出勤簿や休暇管理などのデジタル化を行うことで、勤怠管理事務の効率化を図る。 ※総額 2460万円
★小中学校におけるリモート授業(gigaスクール)の拡充について・・保護者からの要望
市民のみなさんからの予算要望へのご意見のなかから、学校のオンライン通信、タブレット端末のあつかいなどに関するご要望、ご意見をいただきましたので、以下紹介させていただきます(再掲、匿名希望)。
●保護者の声・・・せっかくノートパソコンが各児童のみなさんに貸与されたにも関わらず、意味を成さない運用の仕方をしているように感じられますので、これを是正してほしいものです。また一部の家庭より無線LANの環境が整っていないという意見もあるようですが、必要なものであるので用意して欲しいとの立場を明確にすべきではないかとも思います。各市町村で対応にバラツキが出ている事自体も課題ではないでしょうか。(保護者の要望より)~
※府中市の教育委員会では、通信環境のない家庭には、モバイルルーターの貸出しをしているとのことです。②タブレット端末がいじめの温床にならないように
●保護者の声・・・タブレットの扱いは問題があります。私の子どもの担任は始めてタブレットを配ったときに『クラス内でお互いをカメラで取り合おう』と指示をしたが、息子の弱点をとった生徒がいて、息子は泣いて帰ってきました。先生が生徒同士のトラブルを引き起こす原因にもなりかねません。町田市ではタブレットでの書き込みによる児童へのいじめが発覚、女子児童の尊い命が失われました。府中市でもタブレット端末の扱いについては、様々注意する必要があります。(保護者の声)
★「なりすまし」を防止するためにもQRコードでなく、本人認証のやり方を
●教育委員会の見解・・・本来はQRコードによる認証方法ではなく、本人認証のやり方がよいと、担当者の方も話していましたが、今はコスト上の問題でQRコードを認証のやり方を採用しているそうです。いずれは本人の顔か指紋による本人認証のやり方にしたいとのことでしたが、予算との関係があり早急には変更はできないようです。
さらにタブレット端末のQRコードを偽装できる危険性について、「なりすまし」ができる可能性があり、その点については教育委員会としても警戒しているそうです。以前ですが、町田市の小学校において、児童に配布しているタブレット端末を通じて、「なりすまし」によるいじめが発生し、町田市の女子児童が自殺した事件もあっただけに、教育委員会としても注意しているようです。ただ現状、学校内での「なりすまし」はありえないとのことです。こうしたICT機器について、どういう形であれ、「なりすまし」が起こらない可能性もなくはないと、私は思います。町田市のような事件を繰り返さないためにも、ぜひ決算委員会においても、タブレット端末の本人認証のあり方について、質疑をして求めたいと思います。(府中市議 国民民主党 ゆうきりょう)
※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp 電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202