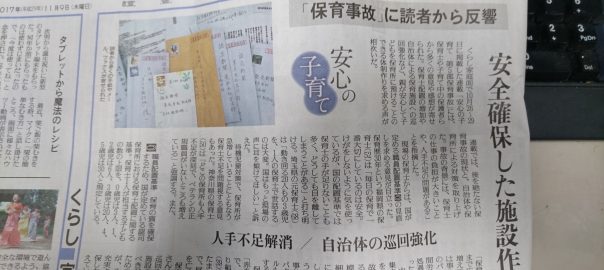横浜市がひとり親家庭の支援のために、日本シングルマザー協会と連携協定締結
今日(2月28日)、横浜市は、「ひとり親家庭の支援に取り組む各種団体・企業と『ひとり親家庭の自立支援に関する連携協定(通称:ひとり親応援協定)』を結び、連携強化の取組をすすめていく」と発表しました。続いて、「その第一号として、『ひとり親コンシェルジュ』事業に取り組む一般社団法人日本シングルマザー支援協会(横浜市神奈川区 代表 江成 道子)と、ひとり親家庭の支援に資する各種取組について連携協定を締結することとなりましたので、お知らせします。今後、本協定をベースとして、様々な取り組みの実施や検討をすすめ、ひとり親家庭を社会全体で支援していく機運づくりに取り組んでいきます」としています。
経緯
「横浜市では、行政による支援の取組だけでなく、民間団体や企業等の有するノウハウを活用することで、よりひとり親家庭への支援が充実し、社会全体でひとり親家庭を支えていく機運が高まるよう、実績のある団体や民間企業と連携協定を締結する枠組みを『ひとり親の自立支援に関する連携協定(通称:ひとり親応援協定)』として創設することとしました。一般社団法人日本シングルマザー支援協会は、シングルマザーの自立を目指し、女性が子どもを育てながらも働きやすい社会づくりを方針に掲げ、当事者目線でシングルマザーに対する様々な支援を行っていますとしています。
連携事項
1.ひとり親家庭への自立支援に必要な情報の提供に関すること
2.ひとり親家庭からの相談に関すること
3.ひとり親家庭への就労支援に関すること
4.ひとり親家庭同士の交流の機会及び場の提供に関すること
※詳細は横浜市のホームページでごらんください。
私も以前から、ひとり親家庭に対する認識を深めるために、岩波新書の「ひとり親家庭」(赤石千衣子著作)を読んだことがあり、また一人親家庭を支援している民間団体の方から話を伺う機会がありました。今回の横浜市の連携協定はひとつのモデルとして参考になると思います。率直に言うと、現在の自治体行政がひとり親家庭に対する施策を行うとすると、かなり限定的かつ否定的な傾向があります。その意味からも、民間任意団体の協力も得ながら、支援策を講じるのはひとつの施策としてありうることと思います。もちろん今後も行政に対して具体的な支援策を要望することは当然ですが、ひとり親家庭の実利実益を少しでも得るために、民間団体などからも、あらゆる協力をえて、そのの生活困窮を打開するために、行政が環境づくりを行うことはすぐにでもできると思います。私もぜひ一度調査して、この問題について議会でも取り上げたいと考えています。