府中市 学童クラブ(放課後児童クラブ)・・学童クラブ利用者の保護者からの声にどう、事業者と行政はどう対応すべきか(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)
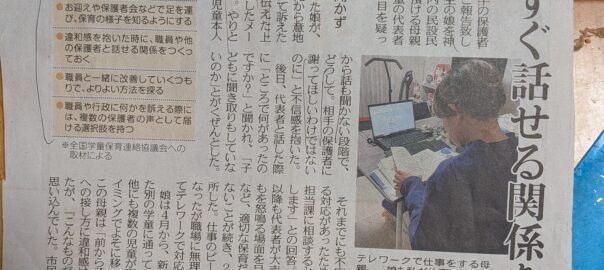
府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
★保護者の意図と違う事業者の対応に不信感
先日の東京新聞に、横須賀市(神奈川県)の民設民営の学童クラブを利用している保護者からの意見、クレームなどに事業者や行政がどう応えるかという視点での記事があります。同記事のなかではその具体例として、「市内の民設民営の学童クラブに小学校の娘さんを預ける保護者の方が、学童内で年上の男児から意地悪をされているとの声を、事業者あてにメールで伝えた」ところ、担当者からは「相手の保護者にクレームを報告しました」との対応がメールで返信された」として、この保護者の方は「児童本人(娘さん)から話も聞かない段階で、どうして(そうした対応をしたのか)。相手の保護者に謝ってほしいというわけではない」と不信感をいだいたとのことです。
また記事では、こうした対応に保護者の方が横須賀市の担当課に相談すると「指導します」との回答だったが、「それ以降も同学童クラブの代表者が大声で子供を怒鳴る場面を目撃するなど、適切な運営だとは思えないことが続き、子どもを退所させた」とのことです。
★保護者と職員との日ごろから対話ができる関係が大事
この記事のなかで、横須賀市学童保育連絡協議会の事務局の方は「子ども同士のトラブルが起きたら、まず本人たちに話を聞いて情報収集し、そのうえで保護者や子どもの気持ちの橋渡しをするのが職員の仕事」と指摘。また記事では全国の学童保育連絡協議会の佐藤事務局次長は「保護者は何かあってから対応するではなく、常日ごろから職員や保護者同士、違和感があった時に話ができる関係をつくってほしい。一緒によくしていこうという気持ちが大事」と話しています。また「学童側と話したり、行政などに訴えたりする際には、『個人ではなく、複数の保護者の声として届けてほしい。そうすることで保護者間で共有でき、その場限りではない、しっかりと対応してもらえる』」と指摘されています。
★「継続的に不適切な事案が発生する場合は、今後、補助金の決定取り消しや不交付も視野に入れて対応を検討」(横須賀市長の議会答弁)
また記事では横須賀市議会で学童クラブの不適切運営を取り上げた市議に対する、上地克明市長はその答弁で「継続的に不適切な事案が発生する場合は、今後、補助金の決定取り消しや不交付も視野に入れて対応を検討する。受け皿の整備も検討し、待機児童が発生しないようする」と答弁。また同市の担当課長も「受け皿がないことが補助金停止の足かせになっていたが、今後は一歩踏み込んでやらねばならない」と話しています。
学童クラブ内におけるトラブル、不適切運営の話題はこの間、あまり表面上、聞くことはありませんでしたが、実際には現場においては様々なトラブル、運営上の問題点があると思われます。今回の東京新聞では、横須賀市のケースをとりあげていますが、府中市内の学童クラブにおける事業者の対応、また不適切運営と思われる運営が表面化した際には、その対応についても、今後注視していきたいと思います。(参考、東京新聞6月記事より)
※学童保育の利用にあたり、保護者が留意したいこと(東京新聞記事より抜粋、全国学童保育連絡協議会への取材による)
①学童クラブはどうあるべきかを知っておくこと。(国や自治体が定める運営指針に記載されている)、②お迎えや保護者会などで足を運び、保育の様子を知るようにする、③職員と一緒に改善していくつもりで、よりよい方法を探る、④職員や行政に何かを訴える場には、複数の保護者の声として届ける選択肢をもつ
※府中市の令和8年度予算案への要望を募集・・・市民のみなさんから要望を受け付けております。9月20日ぐらいまでにメールでお寄せください。匿名希望でも結構です。 ★要望内容の例・・街のライフライン(鉄道駅、バス停車場、道路、信号、カーブミラー設置、公共施設など多数)、市の福祉制度に関すること、小中学校に通うお子さんに関すること、幼稚園、保育所、学童保育、介護、障害者福祉、公共行政のサービスに関することなど、なんでも結構です。※ただし要望内容によっては、私のほうで整理修正、あるいは取捨選択する場合もありますが、どうかご了承ください。 メールアドレス yuki4551@ozzio.jp まで



