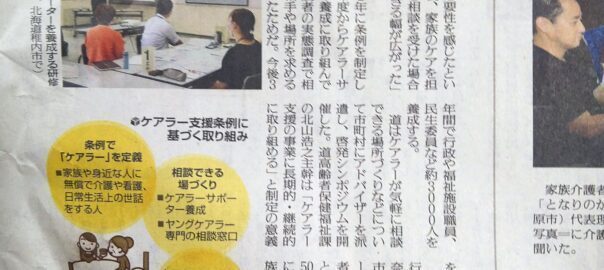(府中市)国がヤングケアラー支援を法制化へ 自治体の実態調査を分析、18歳以上も対象へ(毎日新聞)

府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。今朝の毎日新聞一面に政府がヤングケアラー支援について法制化することを伝えています。
★ヤングケアラー支援はおおむね30歳まで対象
記事によると「政府はヤングケアラーを『家族の介護その他の日常生活の世話を過度に行っているとみとめられる子ども、若者』と定義」、「子ども、若者育成支援推進法」を改正し、実施する見通しとのことです。記事にもありますが、現状、ヤングケアラーを支援する法的根拠がなく、対策が進んでいない自治体が多いことから、法制化によって自治体の取り組み、支援を促進する考えです。また「元ヤングケアラーや専門家からは、家族のケア負担の影響は子どもの機関に限らず、18歳以上になっても進学や就職面などで影響が続く」との指摘から、おおむね30代までを含むとするとのことです。
★「声なきSOS」をどう把握するのか・・国が細やかな調査のもと、支援策を検討へ
ヤングケアラー支援について3面にも特集記事がありますが、「政府が推奨しているのは地域ごとの実態把握だ」とし、「子ども家庭庁によると、23年2月時点で43都道府県、203市町村、12特別区が実態調査をしている」にとどまっており、「地域によって福祉制度や施設、市民活動のレベルなど事情は異なる。細やかな調査は支援策を考えるうえで有効」とし、自治体への調査費補助を増やす方針とあります。
この記事ではヤングケアラー支援策で全国初の条例を制定している、埼玉県の入間市についてふれ、同市ではヤングケアラー支援の啓発動画を作成し、ケーブルテレビや学校での上映会を開催していると伝えています。記事によると「国は自治体の補助金をだし、ヤングケアラー当事者が支えあう『ピアサポート』やオンラインサロンの整備などで、自治体の支援策を後押し』「家族ケアの負担軽減のため家事や育児を手伝うヘルパー派遣も推進」するなどの施策を講じています。
★ 支援策はスピード感より何が有効策か把握する必要がある(こども家庭庁担当者)
ヤングケアラー支援策の推進について躊躇する自治体について、政府関係者は「即効性があり、周囲にとってわかりやすい支援策を提供するのが難しいため、踏み込めない自治体もあるようだ」とし「これまでの支援策はスピード感を重視してきたが、今後は何が有効な手段か把握する必要がある」と分析しています。また記事によるとこども家庭庁は「23年度、各地で行わている支援策の効果測定に取り組み、ヤングケアラーや家族にもたらした影響を調べて整理し、支援効果を高めていく狙いがある」として、結果を24年度に公表するそうです。
★府中市のヤングケアラーの実態調査と相談先について
府中市においても23度の予算案のなかに、大人の代わりに家族の世話や家事を担う「ヤングケアラー」の実態把握と調査について、約570万円の予算を計上することになりました。当時の朝日新聞多摩版でも報じていますが、必要な支援につなぐためにコーディネーターの専門職1人を設置予定で、記事によると「調査は市内の小中高生約2万人と、障害福祉や介護、学校など約100ヶ所を対象にアンケート調査を実施」予定とのことです。ちなみにコーディネーターは市の子育て世代包括地域センターに配置し、相談窓口として周知するとのことです。
★府中市のケアラーワークスの相談窓口(市のHPより)・・家族のケアに関して抱えている悩みの相談を聞き、解決策をともに考えます。
家族のことでモヤモヤしたり、学校のことや将来について心配を感じていたら、電話やメール・SNSで話したり、チャットをすることができます。あなたの希望した場所(学校・家)で話をしたいときは、その場所まで専門相談員が会いにいきます。秘密は守りますので、安心してご連絡ください。大人の方からの相談についても受け付けています。
①相談受付時間・・平日の午前10時~午後5時
②場所・・とりときハウス302号室(宮西町4-13-4)、費用は無料
③相談方法・・電話やメール、LINEでの相談を受け付けています。窓口での相談は事前予約が必要になります。
④電話番号・・042-309-5130、アドレス info@carers.works
★子育て世代包括支援センター「みらい」での相談窓口
①専門相談員によるヤングケアラーや子育て全般に関する相談を受け付けています。
②相談受付時間・・平日の午前8時半~午後6時 施設開館は午前10時~午後6時
③みらい相談窓口・・子育て世代包括支援センター「みらい」(宮町1-41 フォーリス3階)、費用無料
④相談方法・・電話での相談を受け付けています。電話番号 042-319-0072
※ゆうきりょうのブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情などお気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp
★市政の話題など毎日ブログ更新中 検索⇒ ゆうきりょう