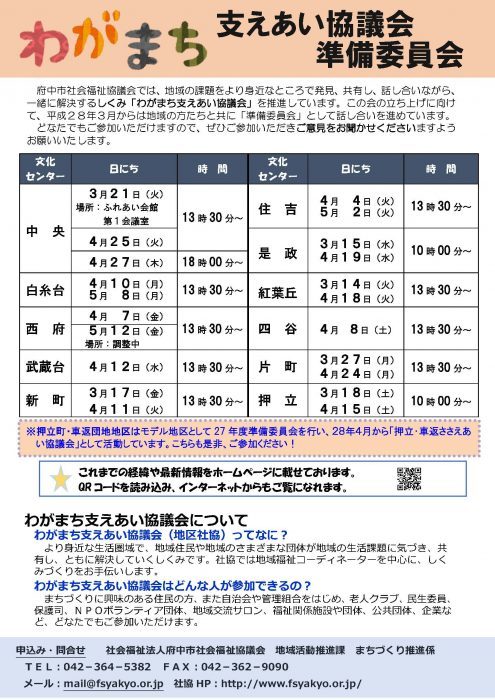「無料低額宿泊所、行政処分7件・・03年策定 国指針拘束力なく」(毎日新聞)
今朝(5日)の毎日新聞朝刊1面に、生活困窮者向けの「無料低額宿泊所」をめぐる記事が掲載されています。それによれば、「国が2003年に定めた運営基準を示したにもかかわらず、自治体による行政処分が今年1月現在、7件にとどまっている」とのこと。このガイドラインについては、いわゆる「貧困ビジネス」(生活保護費から、不当に高額な生活居住費を徴収して、狭隘な施設に住まわせるような実態)を規制するために策定されてものです。この記事では「(国の)ガイドラインに法的拘束力がなく、処分が難しい面があるという。自治体側は10年以上前から毎年、権限強化のための法整備を国に要望しており、国の対応の鈍さが対策の足かせになっている」と書いています。
実は私も府中市内にある生活困窮者を救済援助する、民間任意団体にこの種の話を伺いにいったところ、その責任者の方は「2年ほど前にも貧困ビジネスの犠牲になった方が相談にきて、市に救済支援を求めたが動きが鈍かった」と語っていました。また4月には「貧困ビジネス」の規制条例を制定している、さいたま市にも話を伺いにいったところ、担当課長の方は「こうした規制条例を設けて、これまでのような悪質な貧困ビジネスを摘発する効果を発揮した反面、今度はグレーゾーンもいえる、手の込んだ貧困ビジネスも増えつつあり、それに対する対応策が急がれている」とも語っていました。
今日の毎日新聞では社会面でも、千葉県船橋市の無料宿泊所が国会議員秘書を同席させ、「自治体の行政処分予告に恫喝」との記事も掲載されています。今後、私も府中市でもこの問題を調査し、共産党国会議員団にも国会で取り上げていただき、私も市議会で一度問題にしたいと考えています。